ドイツに来て考える、日本の就職について
 こんにちは、ドイツ・フランクフルトのゲーテ大学に留学中のライターAnです。
私はすでに就職活動を終えており、留学後は日本の金融機関で働くことが決まっています。
今回は、ドイツに来てからずっと考えさせられている、「日本の就職について」改めて考えてみたいと思います。
こんにちは、ドイツ・フランクフルトのゲーテ大学に留学中のライターAnです。
私はすでに就職活動を終えており、留学後は日本の金融機関で働くことが決まっています。
今回は、ドイツに来てからずっと考えさせられている、「日本の就職について」改めて考えてみたいと思います。
「新卒一括採用」「内定」…英語でどう説明する!?
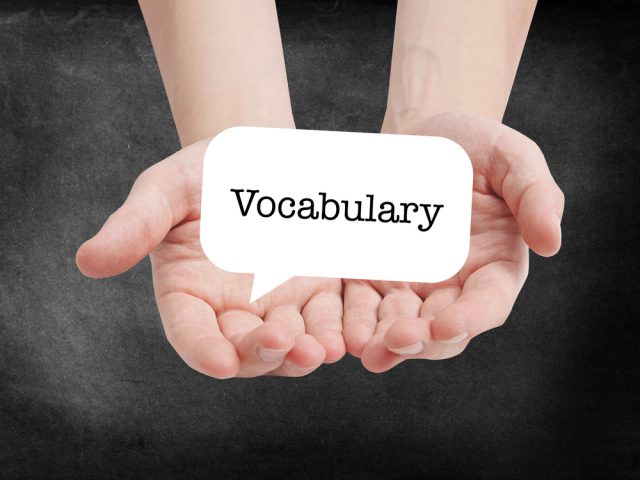 私は現在大学4年生で、今年の3月から6月にかけて就職活動を行い、金融機関に内定をいただきました。
留学先で、授業中に友達ができると、「卒業後は何するの?」という話になることも多いです。
特に私はマスターのクラスも取っているので、将来について考え始めている学生が多くいます。
その中で苦労したのが、日本の就活を英語で説明すること。
「新卒一括採用」「内定」「総合職」「配属リスク」…あなたは英語で説明できますか?
どれも英語に相当する言葉がありません。
徐々に相当する表現が出来るようになりましたが、最初はどう説明したら良いか全くわかりませんでした。
もちろんそれはそもそも、ドイツを初めとするヨーロッパ諸国と、日本の就活が大きく異なるから。
就活だけでなく、就職後のシステムも大きく異なります。
そこで今回は、ドイツに来て考える、日本の就職の”変わったところ”について、お伝えしたいと思います。
私は現在大学4年生で、今年の3月から6月にかけて就職活動を行い、金融機関に内定をいただきました。
留学先で、授業中に友達ができると、「卒業後は何するの?」という話になることも多いです。
特に私はマスターのクラスも取っているので、将来について考え始めている学生が多くいます。
その中で苦労したのが、日本の就活を英語で説明すること。
「新卒一括採用」「内定」「総合職」「配属リスク」…あなたは英語で説明できますか?
どれも英語に相当する言葉がありません。
徐々に相当する表現が出来るようになりましたが、最初はどう説明したら良いか全くわかりませんでした。
もちろんそれはそもそも、ドイツを初めとするヨーロッパ諸国と、日本の就活が大きく異なるから。
就活だけでなく、就職後のシステムも大きく異なります。
そこで今回は、ドイツに来て考える、日本の就職の”変わったところ”について、お伝えしたいと思います。
日本とドイツ、就職の違いって?
1. 「総合職」「一般職」という採用方法
 まず、ドイツには「総合職」という言葉がありません。
総合職として働く、というより「Marketing」「Finance」「Human Resources」として働く、つまり既に会社に入る前から、部署やポジションが決まっているのです。
日本は総合職として入社し、会社の中で様々な部署に異動したり、時には転勤をしたりしますよね。
最近では「ジョブローテーション」といって、あえて2〜3年おきに部署を変えるという取り組みも行われています。
もちろん、それは一概に悪いことではなく、私がとっている経営学の授業の中でも、「ジョブローテーション」は従業員のモチベーションを高める施策として有効とされています。
しかし、ドイツでは専門性を重視するため、一度入る部署を決めたら動くことは滅多にありません。
そのため、「総合職で入社する」「配属リスクがあり部署を選べない」といった日本の状況が、理解しかねるのです。
まず、ドイツには「総合職」という言葉がありません。
総合職として働く、というより「Marketing」「Finance」「Human Resources」として働く、つまり既に会社に入る前から、部署やポジションが決まっているのです。
日本は総合職として入社し、会社の中で様々な部署に異動したり、時には転勤をしたりしますよね。
最近では「ジョブローテーション」といって、あえて2〜3年おきに部署を変えるという取り組みも行われています。
もちろん、それは一概に悪いことではなく、私がとっている経営学の授業の中でも、「ジョブローテーション」は従業員のモチベーションを高める施策として有効とされています。
しかし、ドイツでは専門性を重視するため、一度入る部署を決めたら動くことは滅多にありません。
そのため、「総合職で入社する」「配属リスクがあり部署を選べない」といった日本の状況が、理解しかねるのです。
2. 「新卒一括採用」という採用時期
また、ドイツの企業の多くは通年採用を行っており、中途だろうが卒業後ニートをしていようが勉強をしていようが、専門性と実務経験があると判断されれば、採用されます。 実務経験は、インターンシップを通じて身につけることがほとんどです。 マスタークラスにいる私の友人も、「マスターを卒業したらとりあえずプログラムを使って2年インターンして、その後はどうしようかな」と言っていました。 日本ではその真逆。 大学在学中に就活をしますが、そのタイミングを逃すと就職はものすごく難しくなります。 「新卒」という肩書きだけが、自分の価値なのです。また、一度職場を離れた場合、再就職は難しくなっています。 よく考えると、それはとても不思議なことですよね。 もし仕事を辞めた後に再就職したい場合は、専門性をつけて、即戦力を求める会社に就職するのがいいかもしれない、と思いました。3. 大学の勉強と就職先の関係性
 何度も書いている通り、ドイツでは専門性を重視しているので、大学の勉強が仕事に直結します。
私が「来年から銀行で働く」というと、「大学ではFinanceやPricing、Accountingを勉強しているの?」と聞かれます。
私はこちらでManagementの勉強をしているし、日本ではInternational Economicsの勉強をしていました。
そもそも日本には、「専攻」という概念がそこまで強くないかもしれません。
「文学部から銀行に就職する人もいる」と伝えると、大変驚いていました。
日本の社内研修がそれだけしっかりしているとも言えますし、一方で専門性がなく、適性がわからない人を採用してミスマッチを起こすのは、会社と社員、双方にとって不幸であるとも感じます。
また、日本では就職難のイメージが強い院生ですが、ドイツでは専門性の高い人材として大変重宝されます。
何度も書いている通り、ドイツでは専門性を重視しているので、大学の勉強が仕事に直結します。
私が「来年から銀行で働く」というと、「大学ではFinanceやPricing、Accountingを勉強しているの?」と聞かれます。
私はこちらでManagementの勉強をしているし、日本ではInternational Economicsの勉強をしていました。
そもそも日本には、「専攻」という概念がそこまで強くないかもしれません。
「文学部から銀行に就職する人もいる」と伝えると、大変驚いていました。
日本の社内研修がそれだけしっかりしているとも言えますし、一方で専門性がなく、適性がわからない人を採用してミスマッチを起こすのは、会社と社員、双方にとって不幸であるとも感じます。
また、日本では就職難のイメージが強い院生ですが、ドイツでは専門性の高い人材として大変重宝されます。
4. 終身雇用と転職
 日本では終身雇用、年功序列、といった、ひとつの会社に勤め上げるというイメージが強いですよね。
もちろん、最近では柔軟な働き方が勧められており、「ファーストキャリア」「転職市場」といった言葉も一般的。
それでも、まだまだ日本では新卒で入った会社をやめにくいのが事実でしょう。
ドイツでは、専門性と実務経験さえしっかりしていれば、声をかけられて転職というパターンは少なくありません。
「job change」というよりは、「job hopping」という言葉が適切で、より成長出来る環境、より良い待遇を求めて、会社を変える人が多いようです。
日本では終身雇用、年功序列、といった、ひとつの会社に勤め上げるというイメージが強いですよね。
もちろん、最近では柔軟な働き方が勧められており、「ファーストキャリア」「転職市場」といった言葉も一般的。
それでも、まだまだ日本では新卒で入った会社をやめにくいのが事実でしょう。
ドイツでは、専門性と実務経験さえしっかりしていれば、声をかけられて転職というパターンは少なくありません。
「job change」というよりは、「job hopping」という言葉が適切で、より成長出来る環境、より良い待遇を求めて、会社を変える人が多いようです。
5. ワークライフバランス
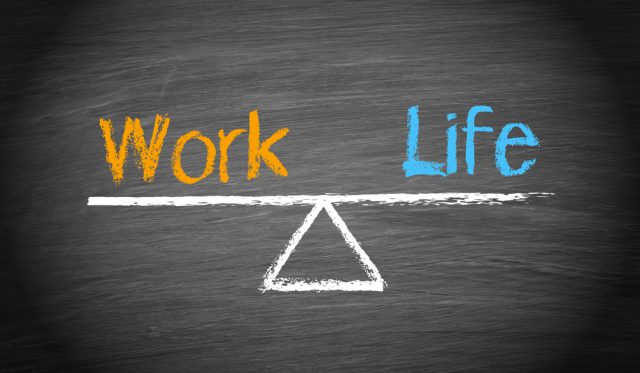 最後に、気になるワークライフバランスについて。
なんと、ドイツでは「終業後に、上司が部下の携帯に連絡をすること」は違法だそう!
そもそも、10時間以上の労働は違法ですし、多くのお店は日曜の営業が違法…。
「絶対に破れない」労働法があります。
日本のように、形だけの労働法ではないのが、うらやましくてしかたありません…。
また、衝撃を受けたのが「転勤がない」ということ。
基本的には転勤はなく、家族は一緒に暮らすもの。
転勤のオファーはたまにありますが、それは昇進やさらなる経験のためです。
しかしそれも、本人の都合で断ることは可能です。
これは中国や、他のヨーロッパ諸国でも同じなようです。
私の友人はインターン中に、ルクセンブルクで単身赴任中の日本人と会ったそう。
「上司からのオファーなので断れなかった」という話を聞いて、大変驚いたようです。
最後に、日本で話題になっている「女性の社会進出」についてですが、ドイツでももちろん似たような問題はあります。
ドイツでは、共働きをしようとすると税金がかなり高くなります。
そのため、子供との時間を大切にしたい女性は、働きに出ないことも多いのです。女性の労働率が男性より低いのは、日本と似た問題ですね。
今回は、ドイツと日本の就職についての違いをお伝えしました。
どちらが良い、とは一概には言えない問題です。
ただ、過労死などの事件が実際に起きていること、多くの家庭が転勤の問題によって苦労を抱えていること、専門性がないがゆえに再就職や転職が難しくなっていること…これらは、一度考えてみるべき問題なのではないかなと思いました。
このように、様々な国の常識を知り、視野が広がることも、留学の醍醐味なのではないかと思いました。
最後に、気になるワークライフバランスについて。
なんと、ドイツでは「終業後に、上司が部下の携帯に連絡をすること」は違法だそう!
そもそも、10時間以上の労働は違法ですし、多くのお店は日曜の営業が違法…。
「絶対に破れない」労働法があります。
日本のように、形だけの労働法ではないのが、うらやましくてしかたありません…。
また、衝撃を受けたのが「転勤がない」ということ。
基本的には転勤はなく、家族は一緒に暮らすもの。
転勤のオファーはたまにありますが、それは昇進やさらなる経験のためです。
しかしそれも、本人の都合で断ることは可能です。
これは中国や、他のヨーロッパ諸国でも同じなようです。
私の友人はインターン中に、ルクセンブルクで単身赴任中の日本人と会ったそう。
「上司からのオファーなので断れなかった」という話を聞いて、大変驚いたようです。
最後に、日本で話題になっている「女性の社会進出」についてですが、ドイツでももちろん似たような問題はあります。
ドイツでは、共働きをしようとすると税金がかなり高くなります。
そのため、子供との時間を大切にしたい女性は、働きに出ないことも多いのです。女性の労働率が男性より低いのは、日本と似た問題ですね。
今回は、ドイツと日本の就職についての違いをお伝えしました。
どちらが良い、とは一概には言えない問題です。
ただ、過労死などの事件が実際に起きていること、多くの家庭が転勤の問題によって苦労を抱えていること、専門性がないがゆえに再就職や転職が難しくなっていること…これらは、一度考えてみるべき問題なのではないかなと思いました。
このように、様々な国の常識を知り、視野が広がることも、留学の醍醐味なのではないかと思いました。

ドイツ留学 関連記事
大学の留学プログラムを使って研究留学しよう! ~留学プログラム・留学先の決め方~
 |
【ドイツに留学したらタンデムを始めよう】留学生活をぐっと充実させるタンデム制度とは?
 |
ドイツ留学の費用を診る、リアルな生活費はいくら?
 |
ドイツ留学のここがオススメだよポイント5

|

ドイツでできる留学



